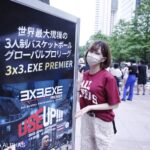トーナメント形式のインターハイは負ければ終わり。しかしインターハイで負けても、次がある。国体は年齢制限をされているにせよ、ウインターカップで借りを返すことができるのだ(もちろん予選を突破しなければならないという注釈は付くが)。インターハイで “敗れてもなお” 、目に留まった選手、チームを紹介していきたい。

「5番と7番と9番の子、いました?」
記憶力の乏しさをひけらかすことになるのだが、昨日の当欄と同じく、今春の能代カップへと話題が飛んだときのこと。
上記の3人はそこにいたかという小生のやや失礼な問いに、コーチは苦笑交じりに「いましたよ。全試合出ていました」。
「申し訳ないけれど、印象にないなぁ……」
頑張っている彼らには申し訳ないのだけれど、しかし今春の彼らにはけっして光が当たっていなかった。
なぜなら「いましたよ、当然でしょう」というコーチでさえ、チーム結成当初は1人の選手を中心にチームを作ろうとしていたと認めているからだ。
市立船橋の話である。
彼らは能代カップにも出場していたが、小生の目に留まったのはキャプテンで、ポイントガードの髙宮大翔だけ。
当時は彼の孤軍奮闘ばかりが目に留まっていた。
しかし四国インターハイで見た彼らは、あのときとあきらかに違っていた。
もちろん市立船橋の心臓部は今なお髙宮である。
そこは変わらないのだが、能代カップから約3か月で、心臓から送られた血は市立船橋の “四肢” へと送られ、それらがそれぞれに素晴らしいパフォーマーとして機能していた。
5番はパワフルなセンター、永島太一。
7番は身体能力の高いフォワード、佐々木慎太郎。
9番はシューターの飯田碧偉。
そして、能代カップのときは別の理由で(兄が市立船橋出身という話で)記憶に残っていた6番の大澤奏太。
その彼らを背番号4の髙宮が生かしながら広島皆実をリードしていく。
なんだ、能代カップのときとはまるで違うじゃないか。

結果から言えば、タイトルのとおり、彼らは広島皆実に敗れている。
しかも最終盤には集中を切らし、一気に突き放されて、64-93での完敗。
しかし個人の得点を見てみると、多い順から飯田、永島、佐々木と続き、その次に髙宮が記録されている。
そのバランスに、かつての市立船橋 ── いや、ここまで来たらより親しみを込めてイチフナと呼ぼう ── らしさを、どこか垣間見た気がした。
イチフナらしさとはつまり、勝っても負けても最後の最後までチームで熱く戦い抜くスタイル。
そのスタイルに心を揺さぶられた高校バスケファンも多いのではないだろうか。