「自分が何十点も取れるプレーヤーでもないからかもしれないんですけど、どちらかというと流れのあるチームで、意図して狙ったシュートまでたどり着くバスケットが面白いなっていうのもあります。それはセットオフェンスの中ではできることが限られているのかなっていうのは最近のバスケットを見て思っていて。展開も早くなってビッグマンもシャープになって3ポイントを打てて、っていうふうになってくると、どちらかというとカオス的な状況の中で求められる判断力とか、そのチームの息の合う瞬間とか。そういったものがすごく面白いなって思ったりするので、そこをまわせる、そこの起点となれるような選手になれたらいいなっていうイメージはずっと琉球のときから持っています。」
能動的に作り出されたカオスな状態に、全体を調和させていく役割。
おそらく1人で50点、60点と積み上げるよりもさらに難易度が高い作業を彼は自ら買って出る。
それは牧が自分のバスケットボールを決定するためでもある。
「アドバンテージがあるところで攻め続けることが正解なのか。そこがわからなかったなって去年ポイントガードをやって思いました。琉球だったら、1対1の能力で考えたらアドバンテージのあるところが多かったので、そこに預けることが一番得点効率が高いと判断して出し続けるべきなのか。はたまたチームとしてボールを回してやり続けるべきなのかっていうところは自分の中で答えが出ていなくて。(藤田HCのチームでプレーしたら)どんな世界が見えるんだろう、みたいな楽しみがある感じです。」
効率化の罠はいたるところで手ぐすねを引いている。
例えば、近年ではスリーポイントの得点期待値がもてはやされて久しいが、それを受けて闇雲にアテンプトを増やせば間違いなく得点力は落ちる。
期待値の出現前後ではシュートセレクションの基準もディフェンスの優先順位もまるで違い、それは確率に少なくない影響を生じさせ、そしてそのまま実際の得点に反映されるであろうことは想像に難くない。
変わってしまった世界で、過去の数字だけを頼りに行動するのは、江戸時代の地図で東京観光をするようなものなのだ。
牧はコート上のダイナミクスを敏感に察知し、定型的な手続きの限界、論理的な展開の脆弱さに疑念を抱き、別の道の模索を試みる。
その発端は随分と前に遡り、そしてその根源には強い思いも込められていた。
「僕がいた高校、大学って、留学生がいなかったので、(相手チームに)留学生がいると圧倒的にアドバンテージを取られてしまいがちだったんです。でもそこに対してやっぱり全員で戦わなきゃいけなかった。どうそこをずらしていくかみたいなところを考えないと勝てなかったっていうのは、すごくあるのかなと思っています。今まで、どこか一つストロングポイントを見出してそこに執着するようなバスケット感覚を育てられてこなかったから、そういう(全員で戦う)バスケットが面白いと思うのか。ちょっとこれはまだわからないですけど、それはある意味一つのきっかけかもしれません。」
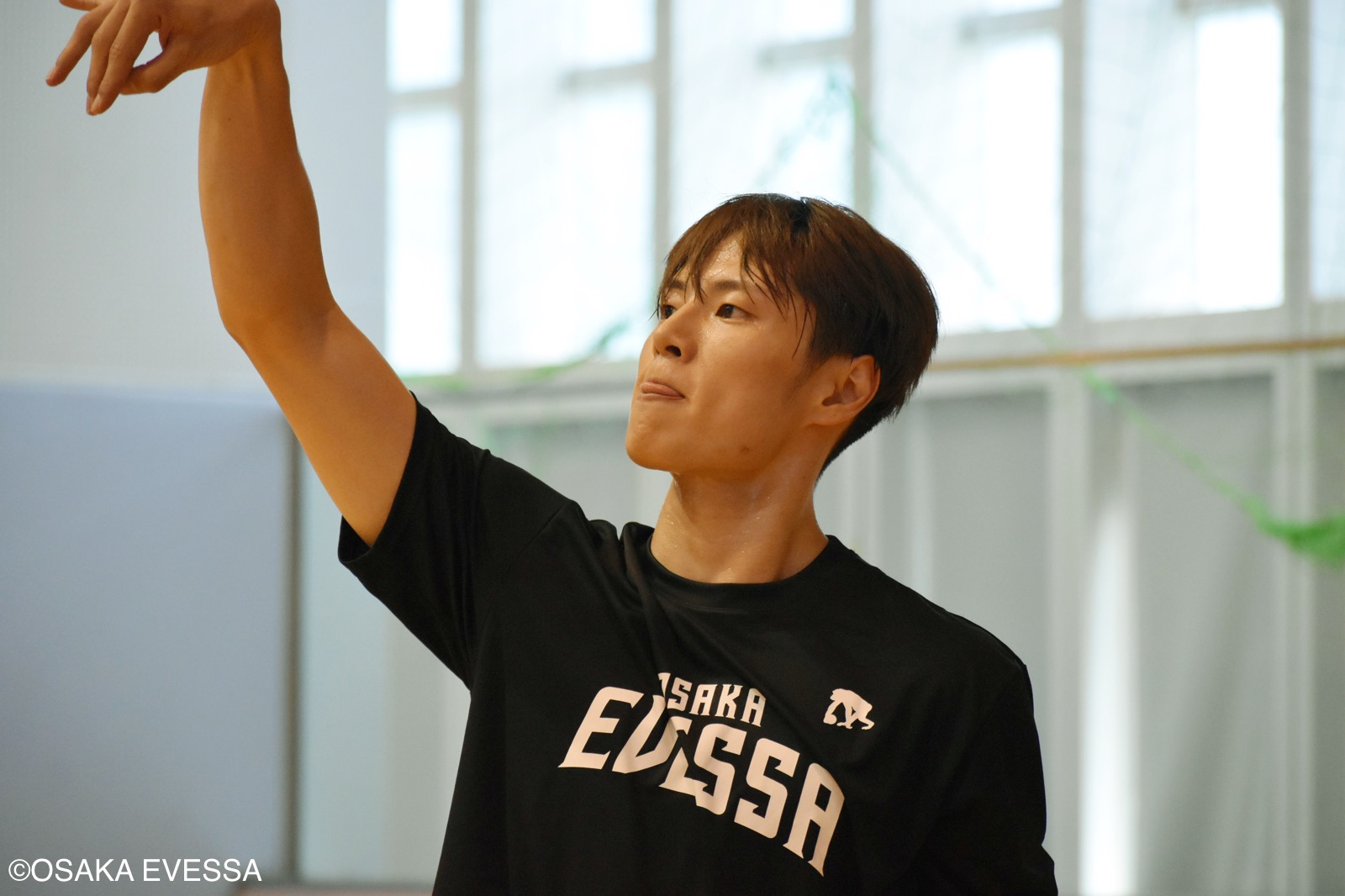
これは核心の一つだと思う。
強力な帰化選手が加入する以前の日本代表が諸外国に対して抱いた劣等感、そして反骨精神。
それを高校生時からすでに経験している世代が、いまや世界と対等に戦うレベルへと昇華されていることは、せんだってのオリンピックを見ても明らかだ。
牧を含む彼らの様々な今後の選択、その一つひとつが、さらに明るい未来を切り開いていくのだろう。
文 石崎巧
写真提供 大阪エヴェッサ






















